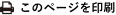小シンポジウム第一次世界大戦研究の焦点をどこに定めるのか-「世界性」と「総体性」そして「現代」の問題性について
山室信一
2010年12月25日
パネラー:大津留厚、中野耕太郎、奈良岡聰智
マルク・ブロックと第一次世界大戦─経験の不確かさと歴史家の務め
2010年11月27日
「アルメニア人問題」の形成とその「解決」
2010年11月13日
賢治と戦争
2010年10月25日
農本主義とファシズム─農業史における第一次世界大戦
2010年10月 9日
文学の「動員」─戦中から戦争直後にかけてのフランス文学
2010年9月27日
第一次世界大戦と東中欧のユダヤ人−−帝国内少数民族から国民国家内少数民族へ
2010年7月12日
日本陸軍は第一次世界大戦から何を学んだか?−小畑敏四郎、石田保政、中柴末純等々にふれながら
2010年6月28日
小シンポジウム「第一次世界大戦と芸術史」
岡田暁生
2010年6月12日
パネラー:河本真理、小黒昌文
大戦を人類学するートレンチ・アートと戦場の記憶
2010年5月24日
アルザスと第一次世界大戦・再考
2010年5月 8日
チャリティからみたイギリスの第一次世界大戦経験
2010年4月26日
間世代的な歴史認識と大戦:北アイルランドのライフ・ストーリーから
酒井朋子
2010年4月10日
報告者は近年、北アイルランドにおいて紛争と社会変動にまつわる聞き取り調査を行ってきた。そのなかで頻繁に出くわしたのが、語り手が両親・祖父母世代から聞いた過去の暴動や戦争の話との関連のなかで自分自身の経験を解釈し、それを通じて(北)アイルランド史についてのメタ・ナラティヴを構築していく語りである。本報告では、このメタ・ナラティヴにおいて第一次大戦がどのように位置づけられているのかに注目する。それを通じて、北アイルランド史において極度に政治化されてきた第一次大戦という歴史的出来事が、その数十年後に生を送った個人の自己形成にとっていかなる重要性をもちえたのかを検討するとともに、個的なライフ・ストーリーと公的記念の交差する地点について考察をくわえたい。
ロシアと第一次世界大戦をめぐる覚え書き−戦争・革命・大学
2010年2月22日
第一次世界大戦と日露関係----『例外的な友好』の真相
2010年2月22日
フェミニストとして、ファシストとして--あるイギリス人女性と世界大戦
林田敏子
2010年2月13日
第一次世界大戦期に、イギリス初の女性警察を率いたメアリ・アレンは、その生涯において、二度、警察に追われた経験がある。一度目は、女性参政権の獲得を目指すサフラジェットとして、二度目は非合法組織に属するファシストとして。「取り締まられる側」から「取り締まる側」へ、フェミニストからファシストへ。めまぐるしく変化した彼女の生涯をたどりながら、「二つの思想」と「二つの大戦」の接点をさぐってみたい。
高橋亀吉の思想的出発─第一次世界大戦後の日本の金融政策のありかたをめぐって
影浦順子
2010年1月25日
本報告では、日本で最初の経済評論家である高橋亀吉の第一次世界大戦後(1920年代~1930年代前半)の論調について考察を行う。日本経済および資本主義経済一般の動きを大胆なヴィジョンに立って総括的にとらえる高橋の経済思想は、これまでジャーナリズムの世界において特筆され、とりわけケインズ主義的な発想を戦前日本に適用した点が評価されてきた。こうした先行研究と報告者の違いは、前者が高橋の経済理論を「○○主義の高橋」として再分析しようとするのに対して、本報告では、高橋が直観的な経済感覚を展開する過程を、当時の日本のおかれた歴史的・国際的文脈や同時代の有識者との論争のなかで実証的に描き出すところにある。先行研究では、あまり触れられることのなかった一次資料を中心に、まず前半では、高橋の経歴(とりわけ第一次大戦前後の活動)と主要著作について概説をし、高橋経済理論の特質について自らの考えを述べる。次いで後半では、戦前日本の最大の金融政策論争であった金輸出解禁問題について、高橋の新平価金解禁論を中心に、その論争課題を再確認したい。そして、その分析のなかで、第一次大戦の終結が日本経済に与えた影響と、その再建のために高橋が提起した日本資本主義の再編方法について考えてみたい。
戦死体はどこへ行く?―追憶のスペクタクル
荒木映子
2010年1月 9日
第一次世界大戦より以前には、兵卒の戦死者に対して公的な記念碑や墓地をつくることはほとんどなかった。ましてや死体がなかったり、あっても誰かわからなかったりする場合には、そのような弔い自体がまれであった。大戦が始まって間もない1915年1月から、イギリスは戦死者の埋葬地を記録する国家的政策にとりかかる。それを任されたのが、当時赤十字社から前線に派遣されていたFabian Wareである。この事業は1917年5月にImperial(現在はCommonwealth)War Graves Commissionとして正式に発足し、死者は戦死した地で埋葬され、国家によって平等かつ永遠に追悼されるべきことが定められた。かくて追憶の民主化は、かつての戦場に長方形の石碑が一様に整然と並ぶ壮大なスペクタクルを生み出した。
英語では、戦争が行われている地域を指して`theatre of war'という表現が1914年から使われるようになった。スペクタキュラーな、劇場的な行為が行われている場所を`theatre'と呼ぶことは、それ以前からあったし、他の言語でもある。戦争に劇場的属性があるとするなら、兵士は戦争という舞台から途中退場してもなお、今度は戦死体としてもう一つの舞台に載せられるということになる。墓地を訪れる巡礼/ツアー客を観客として...。
考えてみたいのは、戦死体の埋葬についての比較文化(日本ではなぜ遺骨収集なのかも含めて)である。時間があれば、戦場ツアー(あるいは慰霊の旅)の持つ意味についても検討したい。
冒頭で竹山道雄『ビルマの竪琴』に言及する予定です。また、報告者が2008年にソンムやイープルで撮った写真と、2008年11月11日にロンドンのセノタフでの90周年の式典を伝えるBBC放送をお見せしたいと思っています。