国際ワークショップ「韓国における軍事基地と反基地・平和運動の現状」
| 日時: | 2013年10月26日 13:30~17:30 |
|---|---|
| 場所: | 京都大学人文科学研究所4階大会議室 |
あいさつ:
田中雅一(京都大学人文科学研究所 教授)
趣旨説明:
朴眞煥(筑波大学留学生センター 研究員)
軍事的な緊張が続く韓国社会では「国家安全保障と平和構築」のために、強い軍事力が必要とされている。そのため、大規模な駐韓米軍基地移転や韓国軍基地建設が計画・実施されてきた。こうした基地移転・建設に伴って環境汚染や生活環境破壊などが深刻さを増している。これらに異議申し立てをするのが非常に困難な状況の中、問題解決に向けて積極的に関わってきたのが平和運動団体である。本ワークショップでは、軍事基地が引き起こす環境問題を「軍事環境問題」と捉え、これらの解決に取り組んできた平和運動団体の活動の事例を通じてその実態を明らかにしたい。さらに、反基地・平和運動を理論的に支えてきた「平和運動論」に焦点を当て、平和運動の限界と可能性を考察する。
パネリスト:
- 「駐韓米軍基地における環境汚染問題と環境運動」/朴鄭璟洙(韓米軍犯罪根絶運動本部 事務局長)
- 「軍事基地建設反対運動の限界と展望――済州島江汀海軍基地建設反対運動の事例から」/崔正玟(Withoutwar メンバー/非暴力プログラム コーディネーター)
- 「軍事安保体制と平和運動――その成果と限界」/李大勲(聖公会大学NGO大学院研究 教授/参与連帯平和軍縮センター 実行委員)
コメンテーター:
- 伊地知紀子(大阪市立大学文学部 准教授)
- 大野光明(大阪大学グローバルコラボレーションセンター 特任准教授)
司会&コーディネーター:
朴眞煥(筑波大学留学生センター 研究員)
国際ワークショップ「韓国社会における軍事基地と反基地・平和運動の現状」報告

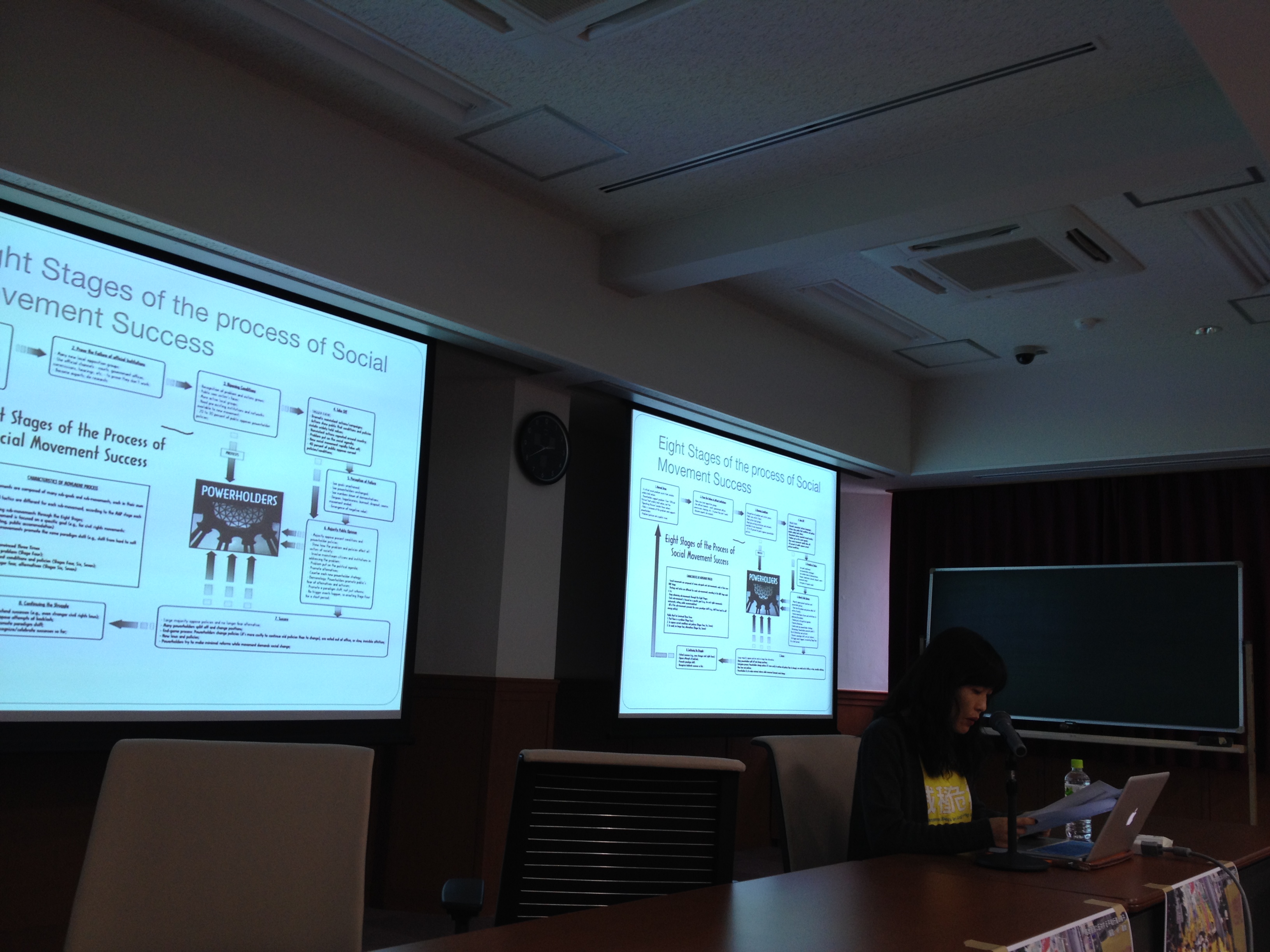
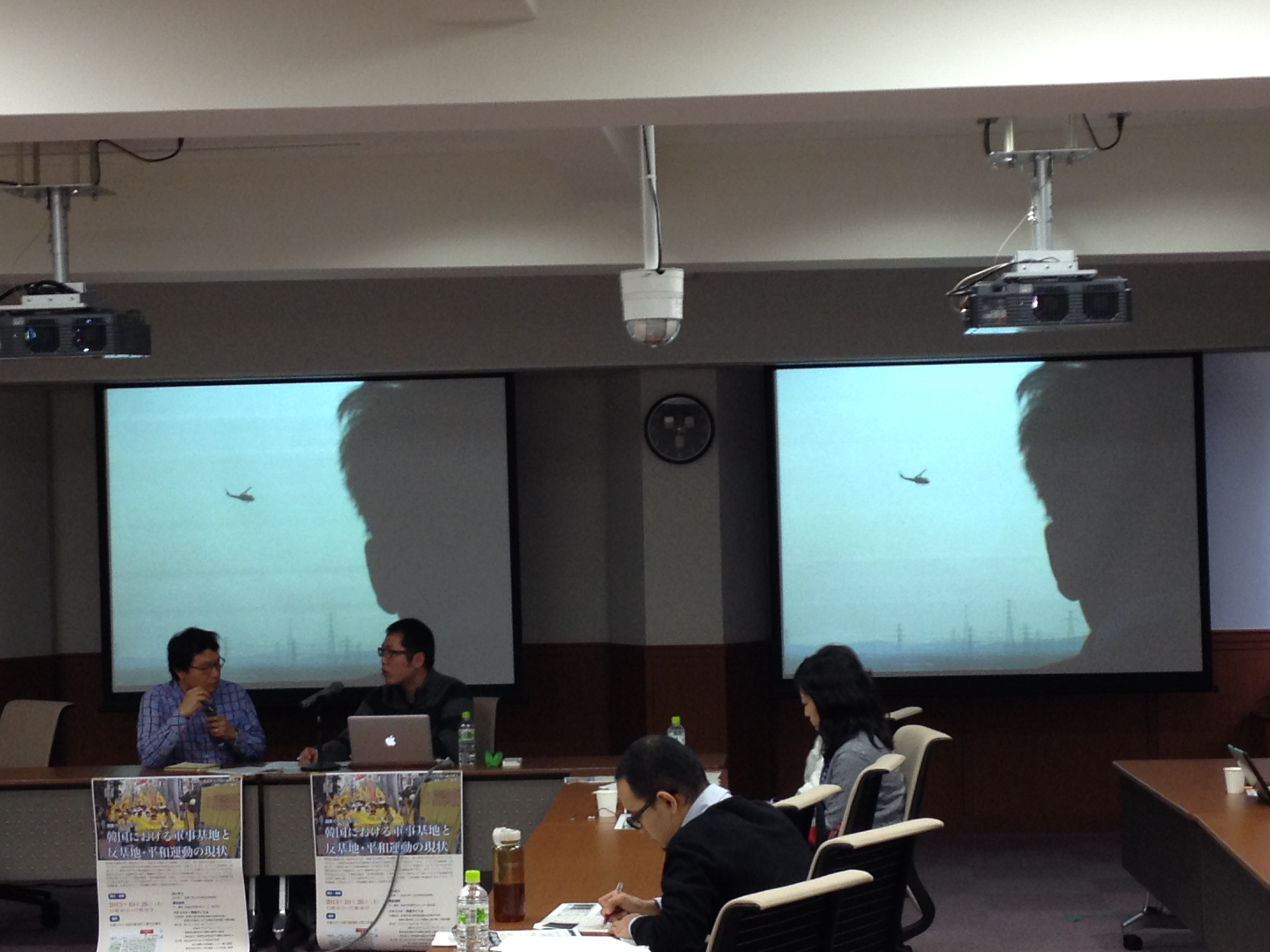
国際ワークショップ「韓国社会における軍事基地と反基地・平和運動の現状」(10月26日於:京都大学人文科学研究所)では、大規模な駐韓米軍基地移転や韓国軍基地建設の計画・実施により環境汚染や生活環境破壊などが深刻さを増す中、これらについて、積極的に関わってきた韓国の平和運動団体の事例や反戦・平和運動の現状についての発表がありました。また、参加者の皆さんと共に韓国と日本における反基地・平和運動について議論し、今日の反基地・平和運動の限界と可能性について考察することができました。
ワークショップでは、まず、駐韓米軍犯罪根絶運動本部事務局長の朴鄭璟洙(パクチョン・ギョンス)氏に「韓国の返還米軍基地と環境運動」についてお話頂きました。2000年前後に起こった駐韓米軍による環境事故の実態や連合土地管理計画などの大規模米軍基地移転事業が計画されるまで、実際に基地返還の過程で明らかになった軍事環境問題の争点を提示して頂きました。
次に、World Without Warのメンバーで、非暴力プログラムコーディネーターである崔正?(チョイ・ジョンミン)氏に、済州島江汀海軍基地建設反対運動の事例からみた「軍事基地建設反対運動の限界と展望」についてお話頂きました。韓国における反基地・平和運動に携わってきた多くの活動家が慢性的な無力感を感じていることや実際に運動が成果をあげているにもかかわらず、それを活動家自身が認識できていない現実を指摘し、Movement Action Planという新たな運動論を提案されました。また、この運動論に基づき、済州海軍基地建設反対運動にはどのような運動団体が参加し、どのように関係していたのか、市民団体が行なった反対運動が済州海軍基地建設反対運動にどのような影響を与えたのかについて分析しました。
三番目に、聖公会大学NGO大学院研究教授で参与連帯平和軍縮センター実行委員である李大勲(リ・デフン)氏から、「軍事安保体制と平和運動――成果と限界」についてお話頂き、韓国社会における平和運動の成果についてご教示頂きました。李大勲氏は、韓国社会における平和運動の成果について、韓国における平和運動の歴史が短いことを指摘した上、平和運動団体が小規模な組織にもかかわらず、軍事主義に反対する多様な実践を行ったことを挙げました。しかし、韓国社会における軍事文化を平和と寛容の文化に変えるためのの課題も示しました。
コメンテーターからは、まず、伊地知氏はMovement Action Planを韓国の社会運動に用いる際、現場に応じた固有性を考慮する必要があることや米軍基地が撤退した後、基地に依存して生活してきた人々についての支援が必要だと指摘しました。大野氏からは、東アジアにおける「脱軍事化」を進める中では「文化」についてのアプローチがますます重要になるのではないかという指定がありました。

