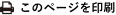メディアについての雑感
(授業見学の感想 兼 ロゴ完成のお知らせ)
世界大戦に関するオンライン研究事典製作のプロジェクト、International Encyclopedia of the First World War に、本研究班のロゴが掲載されることになった。

ロゴのテキストは、Kyoto Seminar for War Studies (略称:KSWS)。
このオンライン研究事典製作プロジェクトは、ベルリン自由大学が中心になって進めており、本研究班のメンバーも執筆、編集にかかわっている。
このたび、ロゴを作成するにあたって、無料で作成できるサイトを利用したのだが、素人のわたしでも、驚くほど簡単にできた。サイトのなかで提供されているいくつかのデザインのなかから使いたいシンボル(イラスト)や文字のフォントを選び、色も自由に選ぶことができる。細かい編集も可能である。一昔前までは、専門家に依頼していた仕事が、程度の差はあれ、いまや無料で誰でもできる。
ほんの少し前まで、いわゆる「コンピューター言語」に精通した専門家にしかできなかった仕事が、簡単な操作でできることにある種の感慨を覚えた。
ありがたい反面、それまで「専門家の仕事」として成立していたことが、なかなか「仕事」として成立しがたくなってきているのも事実であろう(わたし自身、インターネットを通じて無料で開かれている大量の情報の恩恵を被っているひとりである。インターネットによる無料配信が、経済をはじめとするさまざまな格差の溝を多少とも埋める可能性も無視できない)。
興味深いと感じたのは、ロゴの作成サイトにおいて、まず初めに、金融関係、美容関係、アート・娯楽関係、法律関係、教育関係など、およそ30種類のなかから、ロゴを使用する業種を選ぶようになっており、業種ごとにいくつかの画像やフォントがあらかじめ選び出され、カテゴリー化されていることである。 なかには、複数の業種に共通するものもあるのだが、それぞれの業種があらかじめ持っているイメージがあり、文字に書かれた内容だけでなく、フォントや画像からも、人々が総合的に情報を受信/発信していることを示すひとつの例である。また、これらのカテゴリーを利用することによって、知らず知らずのうちに、あるイメージの再生産のプロセスに組み込まれていることを表してもいるだろう。
本研究班のウェブサイトを立ち上げる際、ウェブ製作会社の担当者と打ち合わせをする機会があったのだが、文字のフォントひとつとってみても、分野や業種による違いはもちろん、時代によっても、流行のフォント、レイアウト、色使いがあり、コンテンツも変化しているという話を聞いたことが印象に残っている。
やや大げさな言い方になってしまうが、発信/受信する内容と渾然一体となっているメディア(媒体)を、何らかの形で相対化し、歴史のなかに位置づけようと試みるとき、わたしたちが普段「感性」と呼んでいるものを形成している要素や条件に気づかされることがある(あるいはおそらく「理性」も例外ではない)。
前置きが長くなったが、今月上旬、本研究班のメンバーである岡田暁生による、学部生向けの授業を聴講する機会に恵まれた。世界大戦に関するリレー講義の一環である。
授業の主眼は、まさに、大戦の前後に、メディアの変容によって、とりわけ音楽を通して人々の感性がどのように変化したのか(あるいは、メディアによってつくられた人々の感性が、どのような音楽をつくっていったのか)ということにあったように思う。
1880年代につくられた、SPレコードと呼ばれる初期のレコードは、再生時間が5分ほどであったため、演奏時間が長時間に及ぶクラッシック音楽には適さず、5分以内におさまる音楽がつくられるようになった。
また、1920年代より世界各地で本格的に始まったラジオ放送は、ラジオ放送に映える音楽を要請し、同じ放送圏内にいる人々が同時に同じ音楽や演説を聴くという経験は、ナショナリズムの土壌ともなった(このあたりの事情は、吉見俊哉『「声」の資本主義-電話・ラジオ・蓄音機の社会史』[講談社メチエ、1995年]に詳しい。)
19世紀のヨーロッパにおけるブルジョア階級の音楽と、20世紀のアメリカにおける大衆音楽において、何が変化し、何が変化しなかったのか。
この問いは、授業の初めに提示された、「クラシック音楽とポピュラー音楽は、対立する概念ではない。むしろ兄弟のように隣接する概念であり、もし両者に対置しうる概念があるとすれば、それは民族音楽と呼ばれる音楽である」という岡田の言葉とも呼応している。
授業のなかで何度か使われていた、「音楽の標準言語」という言葉が印象に残っている。
おそらく、現在を生きるわたしたちの大半は、ふたつの世界大戦を経て整形された「音楽の標準言語」のなかで生まれ育ち、標準言語を"話せない"ひと(あるいは自分)を「音痴」と呼んだり、標準言語に翻訳できないものをいつのまにか「音楽」というカテゴリーの外側に追いやったりする思考様式や身体技法を知らず知らずのうちに身につけている。
音楽に限らず、今日の英語も含めた「標準言語」の問題は、帝国主義とわかちがたく結びついており、「標準言語」を形成してきた歴史的な背景をたどることは、「標準言語」に完全に回収されてしまわない、ひとりひとりのなかの雑音(ノイズ)に耳を傾ける作業でもあるだろう。
最後に、筆者が「標準言語」を全否定するつもりではないことを付け加えておきたい。今回のオンライン研究事典も、インターネットの普及と英語によって可能になった、新しい知のあり方であるからだ。もしこの事典がドイツ語だけでつくられた書物だったとしたら、その成果を共有できる人の総数は大幅に制限されることであろう。
重要なのは、「標準言語」によって開かれる世界の可能性を見据えつつ、雑音を完全に消去してしまうのではなく、人間の生み出すざらざらした雑音のなかに広がる、ゆたかな世界をも大切にしていくことではないだろうか。
◆ 日高由貴(京都大学人文科学研究所非常勤研究員|ジャズ歌手)
http://www.niwatoriworks.com/