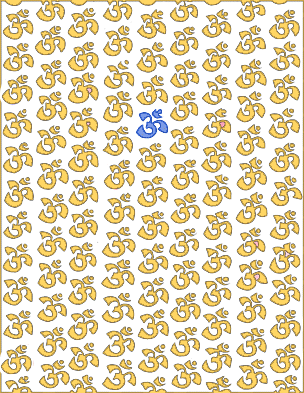 教官・学振特別研究員・院生・研究生紹介
教官・学振特別研究員・院生・研究生紹介
(ただし講座に関係のない人文研の研究生、研修生も含まれています)
教官(詳しくは名前をクリックして下さい)
|
所属部局・身分 |
氏名 |
ローマ字 |
|
人間・環境学研究科教授 |
SUGAWARA, Kazuyoshi |
|
|
人間・環境学研究科教授 |
YAMADA, Takako |
|
|
人文科学研究所助教授・ |
TANAKA, Masakazu |
|
|
人間・環境学研究科助手 |
MATSUMURA, Keiichiro |
★名誉教授
谷 泰
米山俊直
李仁子 (東北大教育学部講師) (LEE, Inja) 博士(京都大学 2002)博論タイトル『移住者の「故郷」とアイデンティティ -在日済州道出身者の移住過程と葬送儀礼からみる「安住」の希求』在日韓国・朝鮮人の生活誌
藤本武 人間環境大学助教授 (FUJIMOTO, Takeshi), 博士(京都大学 2002)博論タイトル『エチオピア西南部マロ社会における農耕の多様性とその構築に関する文化人類学的研究』
Anka Badurina 博士(京都大学 2003)日本の広告代理店の文化人類学的研究 在メキシコ
川村清志(札幌大学助教授) (KAWAMURA, Kiyoshi) 博士(京都大学 2003)ふるさとの表象と実践(日本)
縄田浩志(鳥取大学助教授) (NAWATA, Hiroshi) 博士(京都大学 2003)博論タイトル「乾燥熱帯の沿岸域における人間・ヒトコブラクダ関係の人類学的研究? スーダン東部、紅海沿岸ベジャ族における事例分析から」 牧畜民の文化に関する研究(スーダン、エチオピア)
石井美保(一橋大学講師) (ISHII, Miho) 博士(京都大学 2002)アフリカの複合的宗教文化の研究(ガーナ)
山田仁史 東北大学講師 (YAMADA, Hitoshi) 博士(ミュンヘン大学 2003)世界観・文化史・神話(台湾)
佐藤知久(京都文教大講師) (SATO, Tomohisa) 博士(京都大学 2004)エイズアクティビズム(ニューヨーク、日本)
王柳蘭(助手、アジアアフリカ地域研究科) (OU, Ryuran) 中国系タイ人のエスニシティー(北タイ)
城田 愛(講師、大分県立芸術文化短期大学) (SHIROTA Chika) 博士(京都大学 2005) 踊りにみる越境者のアイデンティティの生成と集団の編成(ハワイと沖縄)詳しくは→
井上卓也(静岡県富士市博物館) (INOUE, Takuya) 山村における生業活動の展開 ー観光産業の導入を契機として(長野県北部)
Marie Luise Legeland(ボン大学社会学日本学科助手)
金谷美和(RPD 国立民族学博物館) (KANETANI, Miwa) 博士(京都大学2005) 職人カースト、国家と「手工芸」形成、物質文化研究(インド)
中谷純江(大阪外国語大学 非常勤講師) (NAKATANI, Sumie) 階級・カースト・ジェンダー日常生活における権力作用(インド)
岩谷彩子(龍谷大学アフラシア平和開発研究センター) (IWATANI, Ayako) 博士(京都大学2005)インドを中心とした商業流浪民、世界のロマ、「ジプシ ー」研究、夢の語り を通した主体の変容
小池郁子(人文科学研究所助教) (KOIKE, Ikuko) サンテリア、アフリカ由来の宗教を実践するアフリカ系アメリカ人コミュニティ
宮西 香穂里(PD 東南アジア研究所) (MIYANISHI, Kaori) ジェンダーから見る米軍基地と地域社会
三田牧(川端牧)(国立民族学博物館 機関研究員) (MITA, Maki) 博士(京都大学 2006)漁民の知識からみた人と海の関係性(沖縄、パラオ)
比留間洋一(静岡県立大学助手) (HIRUMA, Youichi) 子どもの社会化と文化習得、幼稚園と文化(ヴェトナム)
博士後期課程
島薗洋介 (SHIMAZONO, Yosuke) オックスフォード大学留学中 フィリピンの臓器売買
松嶋健 (MATSUSHIMA, Takeshi) イタリアの医療人類学とその実践
増田和也 (MASUDA, Kazuya) 自然利用をめぐる知識・技術と社会関係、農村社会の変容(インドネシア)
藤本透子 (FUJIMOTO, Toko) カザクの家族と子育て
田村うらら(TAMURA, Urara) 市場経済化に伴う貴重財の変遷と現代の様相
〜トルコの「嫁入り道具ceyiz」を事例として〜
山本達也(YAMAMOTO, Tatsya) 北インド・チベット難民のアイデンティティ形成と社会変容
和崎聖日(WAZAKI,Seika) ウズベキスタンのイスラーム社会
梶丸岳(KAJIMARU, Gaku) 音楽のコミュニケーション的様態 中国南部
比嘉 夏子(HIGA, Natsuko) 豚の民族誌(トンガ)
小西賢吾(KONISHI, Kengo)中国少数民族の観光
池田瑞恵(IKEDA, Mizue) 性別の越境は病なのか―「性同一性障害」の構築と診断における解釈枠組みの変遷―
大野哲也 (ONO, Tetsuya) 再生する主体−日本人バックパッカーの「自分探し」の論理から−
徐玉子(SEO, okja) 韓国における基地の女性
陳暢(Chen Chang) 中国の周辺社会におけるマイノリティの言語−中国雲南省シーサンバンナのアカ族の集落を事例に
渡辺文 (WATANABE, Fumi) フィジーにおける「アート」の生成:オセアニアセンターの事例から
池田篤史 マオリの舞踊ハカ
神本秀爾 ジャマイカのラスタファリアン
河西瑛里子 欧米の女神崇拝における癒しの実践 〜イギリスの魔女復興運動の中の薬草利用を 通して〜
福西加代子 博物館における民族表象
山内熱人 メキシコ出稼ぎ移民の向都移動における実存的要因の探求
山野香織 プロテスタント化と酒の社会空間―エチオピア西南部コンタ地域の事例から
中谷和人(なかたに・かずと)病い・障害・技芸―現代日本における障害者芸術/アウトサイダー・アートの人類学的研究
武田龍樹(たけだ・りゅうじゅ)ベトナム南部における仏教の人類学的研究
趙 芙蓉 内モンゴルにおけるシャマニズム復興現象の文化人類学的な研究
博士課程前期(修士)
M4 橋本 章(はしもと・あきら)ブータンの伝統文化における民間信仰の位置付けについて
M3 後藤圭孝(ごとう・よしたか)
M2 Zhai Ruuny(ツァイ・ルーニー)
M2 古阪 馨(ふるさか・かおる)
M2 芦田亮太(あしだ・りょうた)
M2 加藤隆史(かとう・たかし)
M2 関 健次郎(せき・けんじろう)
M2 長谷川アリスン江美(はせがわ・ありすん・えみ)
M2 朴 眞煥(ぱく・じんふぁん)
M2 林 宏壮(はやし ひろあき)
M2 高橋景子(たかはし・けいこ)
M1 飯塚真弓(いいづか・まゆみ)南インド、タミル・ナードゥのバラモン階級の家庭祭礼について
M1 北川 了次(きたがわ・りょうじ)バチカン社会とスイス兵
M1 佃 麻美 (つくだ・あさみ)ペルーにおける牧畜文化
M1 鶴田 宜江(つるた・のりえ)ラトビアにおける宗教
M1 中屋敷 千尋 (なかやしき・ちひろ)インド・チベット社会の宗教実践
M1 萩原 卓也 (はぎわら・たくや)スポーツにおけるジェンダー
M1 秦 玲子(はた・れいこ)
M1 松浦 哲郎(まつうら・てつお)
M1 光保 謙治 (みつやす・けんじ)