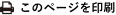開戦100周年の夏に (2):「不毛な戦争」と「正当な戦争」
大戦の開戦100周年を迎えるにあたり、イギリスで最も物議を醸した発言は教育相(2014年7月の内閣改造で離任)マイクル・ガヴによる「左翼学者」批判である。反愛国的な左翼史観によって、「現場を知らないエリート」が無分別に兵士たちを無駄死にさせた、といった「神話」が定着させられた結果、大戦で戦い死んだ「英雄たち」の「愛国心、名誉、勇気」を蔑視する風潮が生まれたというのである。ガヴによれば、ドイツの「無慈悲」で「攻撃的」な「拡張主義」に抗するために参戦したイギリスの決断は、充分に正当であった。「左翼学者」と名指されたケンブリッジのドイツ史家リチャード・エヴァンズ(複数の邦訳がある)の反論は、ガヴの「無知」を一刀両断にしている。大戦を「西欧リベラル秩序」を守るための「正当な戦争」と描きたいのだろうが、イギリスがドイツよりもはるかに専制的だったロシアを盟友としていた事実を理解していない、と。
「正当な戦争」の主張は、他の政治家からも聞かれた。ポピュリスト的な言動で人気を集め、次の保守党党首にさえ擬せられるロンドン市長ボリス・ジョンソンは、大戦が「ドイツの拡張主義と侵略の帰結」だったことは「悲しいが否定できない事実」であると述べているし、イギリス参戦100周年の記念日(2014年8月4日)に、首相デイヴィッド・キャメロンは、「イギリス的価値」「今日のわれわれが大切にしている自由と主権」を守るための決断であったとして、大戦への参戦を明確に擁護した。キャメロン曰く、「無意味な、あるいは自分がなんのために戦っているのかわかっていない人々によって戦われた」戦争だったかのごとく描いて、大戦を貶めるべきではない。
参戦の正当性がかくも声高に語られるのは、イギリスの大戦経験の特異性ゆえのことでもあるだろう。侵攻の危機にさらされていたわけでも、緊急に獲得すべき領土があったわけでもないイギリスは、ベルギーの中立護持といった道徳的な理由を名目に、「自由」「文明」を守るための戦争だとして大戦に参戦した。しかも、1916年まで徴兵制をもたなかったイギリスの戦闘員の43%は志願入隊者であった。差し迫った必要もなしに参戦し、いわば「善意」から従軍した一般国民の膨大な犠牲を招いてしまった結果、大戦をきわめてネガティヴに「不毛な戦争」と見なす傾向がイギリスでは今も強い。戦争の記憶を愛国心やナショナリズムに結びつけたい政治家にとっては、好ましからざる状況である。開戦100周年は、「不毛な戦争」ではなく「正当な戦争」として大戦を印象づけるための格好の機会と見なされたのだ。
1つだけ付け加えておく。「神話」を攻撃する際、「現場を知らないエリート」が無分別に兵士たちを無駄死にさせた、との表現を用いたガヴの念頭にあったのは、アラン・クラークが『ロバたち』(1961年)で用いた「ロバに率いられたライオン」のレトリックだろう。『ロバたち』は、「城の将軍たち」(=ロバ)が豪勢な食事を楽しみつつ発した愚かな命令がライオンのごとく勇敢な兵士たちを大量に死に至らしめた、という今日でも影響力のある大戦イメージを広げることに大きく貢献した本である。「ロバに率いられたライオン」の図式は今日の研究水準において保たれうるものではなく、その意味では「神話」と呼ぶことは可能だが、クラークに「左翼学者」のレッテルを貼るほど的外れなこともない。クラークはヒトラー礼賛まで公言する保守党議員であった。
◆ 小関隆(京都大学人文科学研究所准教授|近現代イギリス・アイルランド史)
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/koseki.htm
開戦100周年の夏に (1):夢の共演?
ヨーロッパの開戦100周年イヴェントを新聞・雑誌で瞥見した限り、やはり目についたのは、ヴェルダン、リエージュ、モンス、等、西部戦線の激戦地における一連のセレモニーだった。イギリスやベルギーの王族も列席する場でイギリス、フランス、ドイツの首脳が握手をし、大戦という苦い対立の経験を直視・克服して今後とも和解と友好を深めよう、との趣旨の演説をする、ほぼ一様にこうした内容である。どうにも気になるのは、自分たちは忌むべき過去を乗り越え、EUを通じて平和的なヨーロッパを実現してきた、というトーンが前面に出されることである(多くのEU懐疑派を抱える保守党主導の連立政権下にあり、EU離脱を唱えるイギリス独立党UKIPが人気を集めているイギリスの場合、EUへのスタンスはやや微妙だが)。EUの達成をどう評価するにせよ、総じて視野がヨーロッパに限定され、ヨーロッパ外にまで思いが至らない印象は否めない。
シンボリックなのが、モンスにおけるセレモニーでベルリン・フィルとロンドン交響楽団が初めて合同演奏をした(厳密には、事前の録音を流した)ことだろう。かつて敵同士として遭遇した戦場で、ドイツとイギリスが今度は平和の調べをともに奏でるのだ。選曲されたのは、ブラームス「ドイツ・レクイエム」の終楽章とソンムで戦死したイギリス人作曲家ジョージ・バターウォースの歌曲集「シュロップシアの若者」、指揮者サイモン・ラトルはベルリン・フィルの監督を務めるイギリス人だから、2つの国の友好を印象づけるうえでたしかに適役といえる。この夢の共演にはヨーロッパの内向きの自己満足が濃厚に漂っているように思えてならないが、しかし注意すべきは、もはやベルリン・フィルもロンドン響も「ドイツの」「イギリスの」名門オケとはもちろん、「ヨーロッパの」それとさえ必ずしもいえないことだろう。たとえば、ベルリン・フィルのコンサートマスターの1人は日本人であり、両オケとも世界中から奏者をリクルートしている。「ピュアなヨーロッパ芸術」は今では想像の中にしか存在しない。
第一次世界大戦が史上初の真の意味での世界戦争であったことを、ここであえて繰り返す必要はなかろう。ヨーロッパで自足する視点をとる限り、過去の直視も克服も十全ではありえない。あるいは、2014年に100周年イヴェントを催すこと自体が、西欧的発想に基づいているのかもしれない。ヨーロッパのいわば「辺境」であるベオグラードに立つ大戦記念碑には、1912 to 1918 との年号が刻まれているという。
◆ 小関隆(京都大学人文科学研究所准教授|近現代イギリス・アイルランド史)
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/koseki.htm