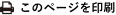メディアについての雑感
(授業見学の感想 兼 ロゴ完成のお知らせ)
世界大戦に関するオンライン研究事典製作のプロジェクト、International Encyclopedia of the First World War に、本研究班のロゴが掲載されることになった。

ロゴのテキストは、Kyoto Seminar for War Studies (略称:KSWS)。
このオンライン研究事典製作プロジェクトは、ベルリン自由大学が中心になって進めており、本研究班のメンバーも執筆、編集にかかわっている。
このたび、ロゴを作成するにあたって、無料で作成できるサイトを利用したのだが、素人のわたしでも、驚くほど簡単にできた。サイトのなかで提供されているいくつかのデザインのなかから使いたいシンボル(イラスト)や文字のフォントを選び、色も自由に選ぶことができる。細かい編集も可能である。一昔前までは、専門家に依頼していた仕事が、程度の差はあれ、いまや無料で誰でもできる。
ほんの少し前まで、いわゆる「コンピューター言語」に精通した専門家にしかできなかった仕事が、簡単な操作でできることにある種の感慨を覚えた。
ありがたい反面、それまで「専門家の仕事」として成立していたことが、なかなか「仕事」として成立しがたくなってきているのも事実であろう(わたし自身、インターネットを通じて無料で開かれている大量の情報の恩恵を被っているひとりである。インターネットによる無料配信が、経済をはじめとするさまざまな格差の溝を多少とも埋める可能性も無視できない)。
興味深いと感じたのは、ロゴの作成サイトにおいて、まず初めに、金融関係、美容関係、アート・娯楽関係、法律関係、教育関係など、およそ30種類のなかから、ロゴを使用する業種を選ぶようになっており、業種ごとにいくつかの画像やフォントがあらかじめ選び出され、カテゴリー化されていることである。 なかには、複数の業種に共通するものもあるのだが、それぞれの業種があらかじめ持っているイメージがあり、文字に書かれた内容だけでなく、フォントや画像からも、人々が総合的に情報を受信/発信していることを示すひとつの例である。また、これらのカテゴリーを利用することによって、知らず知らずのうちに、あるイメージの再生産のプロセスに組み込まれていることを表してもいるだろう。
本研究班のウェブサイトを立ち上げる際、ウェブ製作会社の担当者と打ち合わせをする機会があったのだが、文字のフォントひとつとってみても、分野や業種による違いはもちろん、時代によっても、流行のフォント、レイアウト、色使いがあり、コンテンツも変化しているという話を聞いたことが印象に残っている。
やや大げさな言い方になってしまうが、発信/受信する内容と渾然一体となっているメディア(媒体)を、何らかの形で相対化し、歴史のなかに位置づけようと試みるとき、わたしたちが普段「感性」と呼んでいるものを形成している要素や条件に気づかされることがある(あるいはおそらく「理性」も例外ではない)。
前置きが長くなったが、今月上旬、本研究班のメンバーである岡田暁生による、学部生向けの授業を聴講する機会に恵まれた。世界大戦に関するリレー講義の一環である。
授業の主眼は、まさに、大戦の前後に、メディアの変容によって、とりわけ音楽を通して人々の感性がどのように変化したのか(あるいは、メディアによってつくられた人々の感性が、どのような音楽をつくっていったのか)ということにあったように思う。
1880年代につくられた、SPレコードと呼ばれる初期のレコードは、再生時間が5分ほどであったため、演奏時間が長時間に及ぶクラッシック音楽には適さず、5分以内におさまる音楽がつくられるようになった。
また、1920年代より世界各地で本格的に始まったラジオ放送は、ラジオ放送に映える音楽を要請し、同じ放送圏内にいる人々が同時に同じ音楽や演説を聴くという経験は、ナショナリズムの土壌ともなった(このあたりの事情は、吉見俊哉『「声」の資本主義-電話・ラジオ・蓄音機の社会史』[講談社メチエ、1995年]に詳しい。)
19世紀のヨーロッパにおけるブルジョア階級の音楽と、20世紀のアメリカにおける大衆音楽において、何が変化し、何が変化しなかったのか。
この問いは、授業の初めに提示された、「クラシック音楽とポピュラー音楽は、対立する概念ではない。むしろ兄弟のように隣接する概念であり、もし両者に対置しうる概念があるとすれば、それは民族音楽と呼ばれる音楽である」という岡田の言葉とも呼応している。
授業のなかで何度か使われていた、「音楽の標準言語」という言葉が印象に残っている。
おそらく、現在を生きるわたしたちの大半は、ふたつの世界大戦を経て整形された「音楽の標準言語」のなかで生まれ育ち、標準言語を"話せない"ひと(あるいは自分)を「音痴」と呼んだり、標準言語に翻訳できないものをいつのまにか「音楽」というカテゴリーの外側に追いやったりする思考様式や身体技法を知らず知らずのうちに身につけている。
音楽に限らず、今日の英語も含めた「標準言語」の問題は、帝国主義とわかちがたく結びついており、「標準言語」を形成してきた歴史的な背景をたどることは、「標準言語」に完全に回収されてしまわない、ひとりひとりのなかの雑音(ノイズ)に耳を傾ける作業でもあるだろう。
最後に、筆者が「標準言語」を全否定するつもりではないことを付け加えておきたい。今回のオンライン研究事典も、インターネットの普及と英語によって可能になった、新しい知のあり方であるからだ。もしこの事典がドイツ語だけでつくられた書物だったとしたら、その成果を共有できる人の総数は大幅に制限されることであろう。
重要なのは、「標準言語」によって開かれる世界の可能性を見据えつつ、雑音を完全に消去してしまうのではなく、人間の生み出すざらざらした雑音のなかに広がる、ゆたかな世界をも大切にしていくことではないだろうか。
◆ 日高由貴(京都大学人文科学研究所非常勤研究員|ジャズ歌手)
http://www.niwatoriworks.com/
International Symposium on the First World War and Japanに参加して
9月13日から15日まで、ベルギーで開催された「第一次世界大戦と日本」というシンポジウムに参加した。研究班からは、小川佐和子さんが日本における大戦映画について、荒木映子さんが日赤看護婦について、ヤン・シュミットさん(ボーフム大学)が日本のメディアの大戦受容について、藤原が大戦期食糧問題の日本における受容について報告を行なった。ほかには、皇太子裕仁の欧州歴訪のなかで、ルーヴェン大学に訪れたことについて、とか、ルーヴェン大学の図書館がドイツ軍によって空爆されたあと、日本から多数の本の贈呈があったことに関する報告もあり、大変興味深いものだった。
会議全体を終えて心に残ったのは、大戦後の資本主義国日本の華々しい変貌っぷりと国際的舞台にのし上がるその勢いであった。大戦期の日本について先駆的な研究をしてきたペンシルヴァニア大学のフレデリック・R・ディキンソン氏の報告は、非常に明快であったが、まさにそこに力点をおくものであった。
一方で、資本主義の裏側にある社会主義の問題、あるいは、その運動の展開をとらえないと日本資本主義の特徴がとらえられないのでは、という発言や(藤原)、「民情」という言葉がとらえる権力と民衆のはざまのレベルもとらえるべきでは、という法社会学者の意見(ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーケ氏)もみられた。また、大戦期に本のメディアの送り手だけではなく、受け手についても何らかの方法でみられないか、という意見・質問もシュミットさんをはじめいくつかあった。
以上のような様々な研究者との討論、意見交換は、最近流行のフォーディズム的国際シンポと比べてすさまじく濃密であった。とくにディミトリ・ヴァンオーヴェルベーケ氏は、日本の小作調停法の歴史を法社会学的に研究されておられ(英語の著書をいただいた)、川島武宜をめぐってマニアックな意見交換できたのはとても有意義だった。
なにより印象的だったのは、「口」の力である。しゃべる口と食べる口。欧米の参加者の日本語能力の高さには舌を巻いたし、ルーヴェン大学の方々の食に対する愛着には本当に共感した。合間の食事でちゃんと食材のこと、お酒のことに関するウンチクもじっくり味わった国際シンポジウムはこれが初めてだったからである。アルコール度が高いベルギー・ビール、とりわけトラピスト・ビールを心いくまで味わえたのも、そのウンチクのおかげである。
フィールド・トリップの企画から、さまざまな事務作業まで心づくしのもてなしをしていただいたルーヴェン大学のみなさんにこの場を借りて心から御礼申し上げたい。
◆ 藤原辰史(京都大学人文科学研究所准教授|農業史、食の思想史)
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/fujihara.htm

大戦時にドイツ軍の空爆に遭ったルーヴェン大学の図書館
カピトリーノの丘で第一次大戦を想う
この夏、一週間ばかりローマへ行ってきた。恐らくフランス、イギリス、ドイツなどでは第一次大戦関係の催しが目白押しであるに違いなく、そういうものを訪ね歩くことも考えないではなかったのだが、どこか大戦アニバーサリーのお祭り騒ぎにあまり巻き込まれたくないという気持が働いて、2014年の最初の海外渡航先としてローマを選んだのである。滞在中は主として、サンタ=チェチーリア音楽院蔵のヴェルディのオペラ関係の資料調査という、およそ大戦とは関係ないことばかりしていた。しかし同時にこのローマ行には、カピトリーノの丘で古代ローマの遺跡を眺めながら『ローマ帝国衰亡史』を着想したというギボンに倣い、フォロ・ロマーノで2000余年におよぶ歴史の中での第一次大戦の意味に思いを馳せたいという、幾分ロマンチックな願望も混ざっていた。
案の定ローマには第一次大戦勃発百年の影も形もなかった。ボローニャやパドヴァといった北部の大学町では事情が違う可能性もあるが、ローマでは市当局も大学も博物館も観光局も、大戦などまったく興味がないようである。イギリスやフランス、あるいはベルギーやドイツにおける第一次大戦関係の催しには、多分に「新しい観光資源の開拓」という側面もあるに違いなく、また意識してようがしていまいが、そこには「21世紀における新たなヨーロッパ中心史観を、第一次大戦を軸に組み立て直す/世界にそれを流通させる」という底意が働いていないはずもなく、そう考えるとローマの大戦に対するこの完全な無関心は、むしろ清々しくすらある。この永遠の都にとっては大戦など、人類が古代以来性懲りもなく何度も繰り返してきた愚かな殲滅戦の一つにすぎず、今さら大騒ぎするようなことでもないのかもしれない。
事前に計画していた通り、フォロ・ロマーノのアウグストゥスの宮殿跡あたりの木陰に座って、「古代ローマ人が第一次大戦を知ったらどう思うだろう?」と、色々考えてみた。最初のうちは「ローマ人が知らなかったこと」が色々思い浮かんだ。毒ガス、空爆、潜水艦といった新兵器だけではない。彼らは地球が丸くて有限だということを知らなかった。いくらローマが世界史で最初の超大国/世界帝国だったといっても、その果てにはまだ「外の世界」が広がっていたはずである。ハドリアヌス帝は確かイギリス北部に、異民族の侵略を防ぐ長大な壁を建設したはずだが、これはローマ人が「壁の外の果てしない外部世界」を意識していたことを、逆説的に意味しているのではなかろうか。地の果てまで行けば、壁を超えれば、もちろん恐ろしい異民族やらトラやら狼やらはいるかもしれないが、まだそこには逃げ場がある - これは現代人にはもはやない感覚だ。
だがしばらくするうちに、別の考えが浮かんできた。第一次大戦はそんなにも「未聞の戦争」だったのだろうかという問いである。「現代人が知っていて古代ローマ人が知らなかったのは電気と自動車だけだ」とよく言われる。そして破壊においても、彼らは2000年前に既に、本質的なことはすべて経験し尽くしていたのではないか。古代ローマの建築物で唯一異民族の破壊を免れたものに、有名なパンテオンがある。絶句するほかない建築技術である。今なおまったくびくともしていない。現代の高層ビル解体作業の技術をもってしても、このパンテオンを壊すのには相当苦労するに違いない。してみれば、こうした古代ローマの神殿やバジリカや宮殿や浴場やフォロをあらかた壊し尽くしたゲルマン人たちの「破壊技術」もまた、ローマ人の「建造の技術」に劣らぬ相当な高水準だったと言える。ちなみに古代ローマもまた紀元前に、仇敵カルタゴの都市を完膚なきまでに破壊した。また自然災害としてはベスビオ爆発によって一夜で滅びたポンペイがあるし、「世界が、文明が、一瞬で灰燼に帰する」という感覚は、古代ローマ人にとっても無縁ではなかったはずである。
第一次大戦は人類史上未聞の戦争であったのか。それとも人類が歴史始まって以来延々と繰り返してきた愚行のなれの果てなのか。もちろん私たちが今日直面しているアクチュアルな問題の根っことして大戦を考えるのはとても大事だ。安易にデジャヴュ感を強調しすぎると現代の問題に対する無関心やニヒリズムに陥る。だが同時に、大戦の未聞性をセンセーショナルに喧伝するのではなく、どこかで「同じことの繰り返し」に対する達観と現実主義的な直視を忘れず、そのうえで、「かつてに比べて少しはマシになったこと」を見出し、マシになったその理由を探求する楽天性も忘れたくはない。
言うまでもなくローマはいるだけで楽しい。空気にも街並みにも雑踏にも食事にも、あるいは大学の図書館にすら、至るところに「生きること」の快適な官能が漂っている。「コロッセオある限りローマはある、コロッセオが崩れるときローマも滅ぶ、ローマ滅ぶとき世界は滅ぶ」という有名な言葉をわけもなく反芻しつつ、程よく均衡ある生の快楽こそローマが2000年以上かけて学んだ文明の暴走を制御する術ではないかと思いながら、帰途についた次第である。
◆ 岡田暁生(京都大学人文科学研究所教授|西洋音楽史)
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/okada.htm
開戦100周年の夏に (2):「不毛な戦争」と「正当な戦争」
大戦の開戦100周年を迎えるにあたり、イギリスで最も物議を醸した発言は教育相(2014年7月の内閣改造で離任)マイクル・ガヴによる「左翼学者」批判である。反愛国的な左翼史観によって、「現場を知らないエリート」が無分別に兵士たちを無駄死にさせた、といった「神話」が定着させられた結果、大戦で戦い死んだ「英雄たち」の「愛国心、名誉、勇気」を蔑視する風潮が生まれたというのである。ガヴによれば、ドイツの「無慈悲」で「攻撃的」な「拡張主義」に抗するために参戦したイギリスの決断は、充分に正当であった。「左翼学者」と名指されたケンブリッジのドイツ史家リチャード・エヴァンズ(複数の邦訳がある)の反論は、ガヴの「無知」を一刀両断にしている。大戦を「西欧リベラル秩序」を守るための「正当な戦争」と描きたいのだろうが、イギリスがドイツよりもはるかに専制的だったロシアを盟友としていた事実を理解していない、と。
「正当な戦争」の主張は、他の政治家からも聞かれた。ポピュリスト的な言動で人気を集め、次の保守党党首にさえ擬せられるロンドン市長ボリス・ジョンソンは、大戦が「ドイツの拡張主義と侵略の帰結」だったことは「悲しいが否定できない事実」であると述べているし、イギリス参戦100周年の記念日(2014年8月4日)に、首相デイヴィッド・キャメロンは、「イギリス的価値」「今日のわれわれが大切にしている自由と主権」を守るための決断であったとして、大戦への参戦を明確に擁護した。キャメロン曰く、「無意味な、あるいは自分がなんのために戦っているのかわかっていない人々によって戦われた」戦争だったかのごとく描いて、大戦を貶めるべきではない。
参戦の正当性がかくも声高に語られるのは、イギリスの大戦経験の特異性ゆえのことでもあるだろう。侵攻の危機にさらされていたわけでも、緊急に獲得すべき領土があったわけでもないイギリスは、ベルギーの中立護持といった道徳的な理由を名目に、「自由」「文明」を守るための戦争だとして大戦に参戦した。しかも、1916年まで徴兵制をもたなかったイギリスの戦闘員の43%は志願入隊者であった。差し迫った必要もなしに参戦し、いわば「善意」から従軍した一般国民の膨大な犠牲を招いてしまった結果、大戦をきわめてネガティヴに「不毛な戦争」と見なす傾向がイギリスでは今も強い。戦争の記憶を愛国心やナショナリズムに結びつけたい政治家にとっては、好ましからざる状況である。開戦100周年は、「不毛な戦争」ではなく「正当な戦争」として大戦を印象づけるための格好の機会と見なされたのだ。
1つだけ付け加えておく。「神話」を攻撃する際、「現場を知らないエリート」が無分別に兵士たちを無駄死にさせた、との表現を用いたガヴの念頭にあったのは、アラン・クラークが『ロバたち』(1961年)で用いた「ロバに率いられたライオン」のレトリックだろう。『ロバたち』は、「城の将軍たち」(=ロバ)が豪勢な食事を楽しみつつ発した愚かな命令がライオンのごとく勇敢な兵士たちを大量に死に至らしめた、という今日でも影響力のある大戦イメージを広げることに大きく貢献した本である。「ロバに率いられたライオン」の図式は今日の研究水準において保たれうるものではなく、その意味では「神話」と呼ぶことは可能だが、クラークに「左翼学者」のレッテルを貼るほど的外れなこともない。クラークはヒトラー礼賛まで公言する保守党議員であった。
◆ 小関隆(京都大学人文科学研究所准教授|近現代イギリス・アイルランド史)
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/koseki.htm
開戦100周年の夏に (1):夢の共演?
ヨーロッパの開戦100周年イヴェントを新聞・雑誌で瞥見した限り、やはり目についたのは、ヴェルダン、リエージュ、モンス、等、西部戦線の激戦地における一連のセレモニーだった。イギリスやベルギーの王族も列席する場でイギリス、フランス、ドイツの首脳が握手をし、大戦という苦い対立の経験を直視・克服して今後とも和解と友好を深めよう、との趣旨の演説をする、ほぼ一様にこうした内容である。どうにも気になるのは、自分たちは忌むべき過去を乗り越え、EUを通じて平和的なヨーロッパを実現してきた、というトーンが前面に出されることである(多くのEU懐疑派を抱える保守党主導の連立政権下にあり、EU離脱を唱えるイギリス独立党UKIPが人気を集めているイギリスの場合、EUへのスタンスはやや微妙だが)。EUの達成をどう評価するにせよ、総じて視野がヨーロッパに限定され、ヨーロッパ外にまで思いが至らない印象は否めない。
シンボリックなのが、モンスにおけるセレモニーでベルリン・フィルとロンドン交響楽団が初めて合同演奏をした(厳密には、事前の録音を流した)ことだろう。かつて敵同士として遭遇した戦場で、ドイツとイギリスが今度は平和の調べをともに奏でるのだ。選曲されたのは、ブラームス「ドイツ・レクイエム」の終楽章とソンムで戦死したイギリス人作曲家ジョージ・バターウォースの歌曲集「シュロップシアの若者」、指揮者サイモン・ラトルはベルリン・フィルの監督を務めるイギリス人だから、2つの国の友好を印象づけるうえでたしかに適役といえる。この夢の共演にはヨーロッパの内向きの自己満足が濃厚に漂っているように思えてならないが、しかし注意すべきは、もはやベルリン・フィルもロンドン響も「ドイツの」「イギリスの」名門オケとはもちろん、「ヨーロッパの」それとさえ必ずしもいえないことだろう。たとえば、ベルリン・フィルのコンサートマスターの1人は日本人であり、両オケとも世界中から奏者をリクルートしている。「ピュアなヨーロッパ芸術」は今では想像の中にしか存在しない。
第一次世界大戦が史上初の真の意味での世界戦争であったことを、ここであえて繰り返す必要はなかろう。ヨーロッパで自足する視点をとる限り、過去の直視も克服も十全ではありえない。あるいは、2014年に100周年イヴェントを催すこと自体が、西欧的発想に基づいているのかもしれない。ヨーロッパのいわば「辺境」であるベオグラードに立つ大戦記念碑には、1912 to 1918 との年号が刻まれているという。
◆ 小関隆(京都大学人文科学研究所准教授|近現代イギリス・アイルランド史)
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/koseki.htm