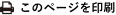9月13日から15日まで、ベルギーで開催された「第一次世界大戦と日本」というシンポジウムに参加した。研究班からは、小川佐和子さんが日本における大戦映画について、荒木映子さんが日赤看護婦について、ヤン・シュミットさん(ボーフム大学)が日本のメディアの大戦受容について、藤原が大戦期食糧問題の日本における受容について報告を行なった。ほかには、皇太子裕仁の欧州歴訪のなかで、ルーヴェン大学に訪れたことについて、とか、ルーヴェン大学の図書館がドイツ軍によって空爆されたあと、日本から多数の本の贈呈があったことに関する報告もあり、大変興味深いものだった。
会議全体を終えて心に残ったのは、大戦後の資本主義国日本の華々しい変貌っぷりと国際的舞台にのし上がるその勢いであった。大戦期の日本について先駆的な研究をしてきたペンシルヴァニア大学のフレデリック・R・ディキンソン氏の報告は、非常に明快であったが、まさにそこに力点をおくものであった。
一方で、資本主義の裏側にある社会主義の問題、あるいは、その運動の展開をとらえないと日本資本主義の特徴がとらえられないのでは、という発言や(藤原)、「民情」という言葉がとらえる権力と民衆のはざまのレベルもとらえるべきでは、という法社会学者の意見(ディミトリ・ヴァンオーヴェルベーケ氏)もみられた。また、大戦期に本のメディアの送り手だけではなく、受け手についても何らかの方法でみられないか、という意見・質問もシュミットさんをはじめいくつかあった。
以上のような様々な研究者との討論、意見交換は、最近流行のフォーディズム的国際シンポと比べてすさまじく濃密であった。とくにディミトリ・ヴァンオーヴェルベーケ氏は、日本の小作調停法の歴史を法社会学的に研究されておられ(英語の著書をいただいた)、川島武宜をめぐってマニアックな意見交換できたのはとても有意義だった。
なにより印象的だったのは、「口」の力である。しゃべる口と食べる口。欧米の参加者の日本語能力の高さには舌を巻いたし、ルーヴェン大学の方々の食に対する愛着には本当に共感した。合間の食事でちゃんと食材のこと、お酒のことに関するウンチクもじっくり味わった国際シンポジウムはこれが初めてだったからである。アルコール度が高いベルギー・ビール、とりわけトラピスト・ビールを心いくまで味わえたのも、そのウンチクのおかげである。
フィールド・トリップの企画から、さまざまな事務作業まで心づくしのもてなしをしていただいたルーヴェン大学のみなさんにこの場を借りて心から御礼申し上げたい。
◆ 藤原辰史(京都大学人文科学研究所准教授|農業史、食の思想史)
http://www.zinbun.kyoto-u.ac.jp/zinbun/members/fujihara.htm

大戦時にドイツ軍の空爆に遭ったルーヴェン大学の図書館