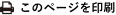音楽におけるナショナリズムの発現形態─ラプソディの歴史と第一次大戦
伊東信宏
2012年12月 8日
音楽ジャンルとしての「ラプソディ」は19世紀中葉、F.リストの『ハンガリアン・ラプソディ』(第1〜19番の大部分は1853年刊行)によって、それまでの素朴な「語り物」的叙事詩から、民族主義的な器楽曲ないし管弦楽曲へと変質する。以後、このような「民族叙事詩」としての各国(各地域/各民族)ラプソディは、世紀転換期から、第一次大戦を超えて戦間期まで陸続と現れることになる。有名なところだけでも、A. ドヴォルザーク『スラヴ・ラプソディ』1878年、G. エネスク『ルーマニアン・ラプソディ第1番、第2番』1903年、ヴォーン・ウィリアムス『ノーフォーク・ラプソディ』1906年、M. ラヴェル『スペイン・ラプソディ』1907-08年、マルティヌー『チェコ・ラプソディ』1918年、パンチョ・ヴラディゲロフ『ブルガリアン・ラプソディ「ヴァルダール」』1922年、G. ガーシュイン『ラプソディ・イン・ブルー(作曲中のタイトルはアメリカン・ラプソディ)』1924年、B. バルトーク『ラプソディ』第1番、第2番1928年、伊福部昭『日本狂詩曲』1935年など。これらの作品群を見ると、民族ラプソディの作曲が、各国語によるオペラの制作や民謡編曲などと並んで、音楽におけるナショナリズムの表現手段のひとつとなっていたことがわかる。同時にここには独仏伊といった国のラプソディが欠けていることも注目に値する。
このようなラプソディの歴史にとって第一次大戦がどんな意味を持っていたか、いくつかの作品を取り上げながら考えてみたい。
アメリカにおける映画・芸術・国家--D.W.グリフィスの場合
石田美紀
2012年11月10日
第一次世界大戦が「芸術」という概念を再編する契機となったことは、よく知られている。しかし、19世紀末に誕生した新しい表現媒体である映画を巡る状況は、旧来の諸「芸術」のそれとは異なっていた。映画は第一次大戦直前に物語を語る媒体として急激に整備され、「芸術」を目指し始めた。とりわけアメリカにおいては、映画にはまだ年若い国家独自の「芸術」としてのあり方が期待され、論じられていた。
本報告では、アメリカ映画の父として知られるD.W.グリフィス作品『国民の創生』(1915)、『イントレランス』(1916)、『アメリカ』(1924)に焦点を絞り、当時の批評言説と突き合わせながら、映画と芸術、そして第一次世界大戦の関係を考察する。
捕虜が働くとき
2012年10月22日
第一次世界大戦前後の史跡・名勝保存と「伝統文化」
高木博志
2012年10月13日
1908年から1910年までドイツ・フランスをはじめギリシャ・ローマなどの博物館や史跡をめぐった東京帝国大学の黒板勝美は、ドイツの郷土保存主義(ハイマートシュッツ)に学びながら、地域社会で文化財を保存する「現地保存」の思想を日本に紹介する。それは大英博物館やルーブル美術館のみならず、明治期以来、帝室博物館や帝国大学に美術品や歴史資料を集積してきた中央集権的で優品主義のありようとは違う、新たな提起であった。1897年の国宝保存法の優品主義に対して、黒板勝美が影響力を持った1919年の史蹟名勝天然紀念物保存法においては、地域社会とかかわりをもち、府県に主体性をもたせる新たな文化財行政が生み出された。報告では、以上の主題に加えて、この時期に模索される「日本らしい」文化財である名勝・「文化的景観」の保護や皇室財産の文化財(陵墓や御物)の権威化の問題を考えたい。また地域社会での文化財の保護や顕彰は、郷土主義や「お国自慢」とかかわり、観光と連動してゆく。そして現代につながる宗主国と植民地(エルギン・マーブルなど)、東京と地方といった国内外を貫く、文化財の返還運動にも言及したい。
講演会「Russian to Polish to Soviet : Vilnius in Two World Wars」
2012年9月29日
フランス植民地から考える第一次世界大戦と歴史認識
平野千果子
2012年9月22日
国際体制の転換点とされる第一次世界大戦を、フランス植民地を軸に見直すと、どのような論点が浮かび上がるだろうか。
本報告では、フランス植民地、なかでもサハラ以南アフリカを中心に、大戦中のフランスの行動、また戦後の状況から、考察してみたい。
「帝国の総力戦」と恒久平和の夢-大戦間期イギリス帝国にとっての国際連盟~
津田博司
2012年7月14日
今回の報告では、近著『戦争の記憶とイギリス帝国』で論じた、大戦間期のイギリス帝国における大戦の記憶を背景に据えながら、悲惨な大量殺戮の経験が意味づけられ、新たな世界秩序の担い手としての国際連盟が希求される過程について、考察します。
具体的には、まずディキンソンなどの代表的論者の言説を通して、(後世から見れば、その挫折が運命づけられている)国際連盟がどのような可能性をもつものとして構想されたのか、その同時代的文脈を検証します。さらに、絶対平和主義や集団安全保障といった思想の間に存在した、相反する複数の国際連盟観に着目することで、当時の人々がどのような論理に基づいて、次なる戦争を迎えるに至ったのかを跡づけたいと思います。
パレスチナ移民と「イスラエルの残り」――大戦下のユダヤ・メシアニズム
向井直己
2012年6月25日
一般に、第一次大戦はユダヤ史の近代と現代を画する事件とみなされています。「長い19世紀」を通じてヨーロッパ各地で進行した同化の潮流は大戦を機に衰微する一方、バルフォア宣言において一つの現実的可能性を提示したシオニズムが、ユダヤ人の間で徐々に勢力をのばしてゆく、という具合です。こうした過程が統計的に確認できるかはさておき、「ユダヤ」をめぐる当人たちの言説のトレンドがこうした形で変化していったことは間違いないかと思います。近年手厳しく批判されている、ディヌール、バエル、ショーレムといったエルサレム学派の台頭も、戦後のこうした空気のなかで改めて理解されるべきものでしょう。
この報告においても、シオニズムと同化という二つの潮流の交錯点として第一次大戦をとらえることから出発したいと思います。報告の前半はオデッサ出身のシオニスト、ゼエヴ(ウラディーミル)・ジャボティンスキーの活動を中心に、当時のユダヤ人がおかれていた国際政治の状況を俯瞰するつもりです。修正主義(≒武闘派)シオニストの祖として何かと悪名高いジャボティンスキーではありますが、7ヶ国語を操り、ジャーナリストとして各地を遍歴した彼の国際的な感覚は、とりわけ大戦中機能停止に陥っていた世界シオニスト機関の幹部らと比べますと、きわめて鋭敏かつ現実的であった様に思われます。彼の働きかけによって英国軍内に創設された「ユダヤ人部隊」は、ほぼ2000年ぶりにユダヤ人が「ユダヤ人として」武器をとった事例であると言われています。その後部隊はアレンビーのパレスチナ遠征に途中参加し、その一部はパレスチナに留まって、現在のイスラエル国防軍 の基礎を築きました。報告においては、彼の回想録『世界戦争におけるユダヤ人部隊』(1930;英訳1945)を軸に、ユダヤ人に対してパレスチナ移民/ 植民が持つ意味、またそれが国際政治のなかで担う役割を確認してゆきます。
ジャボティンスキーのユダヤ人部隊創設活動は、戦中にはシオニストを含め、ヨーロッパ中のユダヤ人から敬遠されました。報告の後半では、こうした「抵抗」の根を探ってゆきたいと思っています。シオニストらの抵抗は、政治状況の不安定性に由来するところが大きい様に思いますが、彼らに「同化主義者」と揶揄されるリベラル派の抵抗は今少し根が深く、国家と倫理の関わりに関する理論的な構想を背景においています。倫理の絶対性と普遍性を基盤に、あえて諸民族・諸国家の間に留まり続けるという「同化主義者」の構想は、よく引き合いにだされる「三つの誓い」のような宗教的信条にのみ還元されうるものではありません。メシアの到来を倫理の完成=諸民族の調和として理解したリベラル派の政治的-神学的思考は、「諸民族の戦争(Voelkerkrieg)」とも呼ばれた大戦の中で、独特の深化をとげてゆきます。イギリスが主要な役割を果たす前半の報告を補足する意味でも、後半ではドイツにおける議論、とりわけ『ユダヤ教原典に拠る理性の宗教』(1919)に結実してゆくヘルマン・コーヘンの議論を参照しながら、大戦を機に凋落していった、ユダヤの或るメシアニズムについてご紹介させていただければと思います。
大戦期日本の郷土誌編纂
黒岩康博
2012年6月 9日
大戦期の日本を訪れた空前の郷土誌編纂「ブーム」。それらを素材に、「郷土」の一次大戦認識を探る。
カフカスと東アナトリアの戦線─「諸民族のルネサンス」
伊藤順二
2012年5月28日
ロシア帝国崩壊後のメンシェヴィキ・グルジア共和国の首相となるノエ・ジョルダニアは、1915年の論説で同時代の趨勢を「諸民族のルネサンス」と形容している。戦争の初期にジョルダニアは戦争協力を容認し、その意見はグルジア・メンシェヴィキ主流からは問題視されるが大衆的支持を得ていた。グルジア人の懸念は、崩壊が確実視されていたオスマン帝国に併合されることではなく、戦争に対し極めて積極的なアルメニア人のいわゆる「大アルメニア」構想に飲み込まれることにあった。一方、アルメニア人活動家はグルジア人と「アゼルバイジャン人」との共同を危惧していた。
オスマン帝国がロシアに宣戦布告するのは1914年10月末のことである。両帝国が接するカフカス・東アナトリア戦線は、いわゆる西部戦線・東部戦線・バルカン戦線の状況を横目で見据えつつ、3ヶ月の猶予期間をもらっていたことになる。この時期に各陣営は来たるべき戦争への展望と準備を固めていた。また、1912年頃から、すなわちバルカンが2度の戦争を経験していた時期に、この地域でも両帝国によるアルメニア人やクルド人への働きかけが活発化している。実は同時期に、バクーやチフリスやグルジアの鉱山などのロシア領カフカスにおける労働運動も1905年革命以来の盛り上がりを見せている。しかし形式的には「万国のプロレタリアート」の団結を標榜していた社会主義者の運動は、少なくともバクー以外では超民族的運動として結実してはいない。
東アナトリアは少なくとも1877年の露土戦争以来、国際的注目の的となっていた。各国の介入は現地住民の離間を一層促進した。カフカス・東アナトリア戦線の状況とその帰結は、帝国による分断統治の顕著な成功例とも言えるだろう。報告では開戦前から開戦初期にかけてのこの地域の情勢を俯瞰し、アルメニア人虐殺をもう一度歴史的に位置づけてみたい。
ドイツ戦争精神医学と"精神分析療法の道"
2012年5月12日
チェコスロヴァキア軍団と日本─1918-1922年
林忠行
2012年4月23日
第一次世界大戦期にロシアで移民や捕虜によって組織されたチェコスロヴァキア軍団は、1918年5月以降、ウラル、シベリア地域でボリシェヴィキ政権との軍事衝突に陥り、その結果としてロシア内戦に深くかかわりを持つにいたった。日本は、この軍団の救出を口実として1918年8月に米国とともに「シベリア出兵」を開始するが、現地での軍 団と日本軍との関係は次第に悪化し、軍団がロシアから撤退する過程にあった1920年4月には軍事衝突も起きた。その背景には軍団がロシア人、朝鮮 人、中国人などの反日勢力と結びついていたという事情があった。この報告では、ロシアでの軍団の編成から撤退までの経緯を、とくに日本との関係に視点をおいて報告した。
ドイツ自然療法運動の第一次世界大戦への道 ─医療「アウトサイダー」から大戦下「動員」へ
2012年4月14日
補給戦と合衆国
布施将夫
2012年2月27日
第一次世界大戦に合衆国が参戦したのは、ドイツに対し宣戦した1917年4月のことであった。その交戦国ドイツは、大戦前から壮大な戦争計画シュリーフェン・プランを作成し、この計画を改めながら大戦を戦った。しかし、マーティン・ファン・クレフェルトの『補給戦』は、シュリーフェンが「補給軽視」であったため、ドイツは「敗けるべくして敗けた」と結論付けている。では当時、勝者となった合衆国の補給戦は、いかなるものであったのか。クレフェルトは、後のノルマンディー上陸作戦における連合国の補給戦については比較的高く評価しているものの、第一次大戦期の合衆国の補給戦については沈黙している。また合衆国は、「すばらしき小戦争」と形容された1898年の米西戦争の間でさえ、補給の失敗を経験していた(肥後本芳男他編『アメリカ史のフロンティアII 現代アメリカの政治文化と世界-20世紀初頭から現代まで』昭和堂、2010年、10-13頁参照)。そこで本報告では、米西戦争と第二次大戦という第一次大戦を挟んだ二つの戦争で、補給に関し相反する評価をされた合衆国が、第一次大戦期にはどのような補給戦の計画・実践を行ったのかを考察したい。
本報告では、合衆国による補給戦の海上計画と陸上実態で、内容を前後半で分ける予定である。第一次大戦以前の合衆国の仮想敵国は、20世紀初頭の日露戦争や日米移民問題が契機となって、ドイツよりもむしろ日本であった。こうした日本に対し、合衆国海軍では「オレンジ・プラン」が作成されていく。そこで報告前半では、この計画に関する決定的研究とされた参考文献の書物を中心に、1906年から22年までのオレンジ計画を概観する。そして報告後半では、大戦下の合衆国内における陸上補給の実態を取り上げる。対独計画ブラックを含む大西洋方面の戦争計画はなきに等しいとされたが、その一方、国内の陸上輸送は円滑に進んだのか。1917年末に鉄道庁が新設されたのは、陸上輸送問題を救済するためではなかったか。こうした問題意識をもって、大戦下の行政の対応を再考しよう。
クルーシブル(坩堝)─第一次世界大戦とアメリカニズム
中野耕太郎
2012年2月11日
第一次大戦への参戦は、20世紀アメリカの外的膨張と内的統合の歴史において大きな転機となった。初めて欧州に大規模な派兵を行ったアメリカはこの行為を正当化するために、戦争目的を専制と民主主義のイデオロギー闘争と位置づけ、戦後の世界秩序の構築にあたっては、被抑圧諸民族の解放を前提とする民主的な平和をその基軸理念に掲げていた。だが同時に、この時期のアメリカは、メキシコやハイチ、ニカラグアなどに苛烈な軍事干渉を繰り返すなど、自身が否定したはずの典型的な帝国主義国としての相貌を持ち合わせてもいる。むしろ参戦に至る経緯をつぶさに見るとき、アメリカが米西戦争以来、築いてきた「帝国」としての実績こそが、元来「外部の戦争」たる世界大戦への参入を強く促したことがわかる。しかし、それにもかかわらず、アメリカは終始、無賠償の講和、民族自決、国際連盟といった理想にこだわり続ける。第一次大戦の炎の中で、「世界」との相互関係を深め、グローバル国家になろうとしていたアメリカは、複数の異なる行動原理と政治理念を体現するプロテウス的なパワーであった。
同様の多面性は、戦時下の国家動員政策にも看取される。参戦期のアメリカでは、規律と奉仕の精神を鼓吹する権威主義的なナショナリズムが台頭する一方で、戦時行政の徹底した情報開示や広報活動に依拠した世論形成に多大なリソースが投入されている。戦争協力を自発的な「被治者の同意」によって担保しようとする、いわば「民主的」愛国の潮流である。ふたつのナショナリズムは、特に徴兵制度のあり方や、徴兵を通じた社会・国家関係において対立する局面が少なくなかったが、ある種の理想を共有していた。それは、戦時動員が多様な人々をひとつの「国民」に包摂し、統合することを目指しているという社会的コンセンサスだった。権力的統治と民主化の約束、それに立脚した国民形成は、女性や黒人、移民といった周辺化された人々の戦争へのコミットメントに複雑な影を落としていた。
本報告では、具体的に黒人と東欧系移民の、1. 戦争プロパガンダとの関わり、2. 徴兵の実態、3. 軍隊内部での処遇を検証し、総力戦の坩堝の中で鋳造されつつあった新しいアメリカ国民国家を考察する。第一次大戦期のアメリカ軍に動員された外国籍の兵士と黒人兵士の数は、それぞれ約50万人と40万人(合計すると全兵士数のおよそ3分の1)に達したのであり、彼らの従軍経験とこれを組織した軍の制度は、20世紀アメリカニズムの想像力を大きく規定しただろう。ここでは、各エスニック集団の文化生活に一定の承認を与えつつアメリカ人意識の浸透を目指す多元的国民統合論と、有色人を国民内の「他者」として位置付ける人種隔離の統治技法が重要な争点として浮上してくる。なお、本報告の検討では、上記3点に加えて、4. 国外の民族独立や反植民地闘争とも深く関わった移民や黒人指導者の戦争観(戦後の夢)にも注目し、アメリカの国民形成が、前段でふれた民主的平和の国際大義と密接に関わっていたことを確認する。
支配と解放の2つの顔をあわせ持つアメリカニズムのプロテウス的性格――それは、第一次大戦中・戦後のアメリカと世界に洗練された統治権力(秩序)を構築するが、時に隠しおおせない矛盾と欺瞞のシステムとして弱さをさらけ出した。その間隙は、いずれ植民地ナショナリズムや国内マイノリティの異議申し立てが重要なエージェントとして台頭する20世紀史の豊かな歴史ダイナミズムの源泉ともなるだろう。
小シンポジウム「帝国を使いつくす─第一次世界大戦と植民地統治」
伊藤順二
2012年1月28日
パネラー:石井美保、堀内隆行
ヨーロッパ統合史は可能か
遠藤乾
2012年1月14日
この報告では、歴史叙述の方法論について、若干特異な素材である欧州連合(EU)を取り上げて、考え直してみたいと思います。
おそらくこの素材は、日本や欧州(のどこかの大国)の1~2世紀前の思想や社会の状況と異なり、歴史や文化の伝統の深い京都で最も尊敬されないテーマに違いありません。第一次大戦のような大きな出来事とのつながりもなんら保証されていません。
この報告は、そうした自動性のない素材を取り上げ、それ故にあるだろう困難を語ることになります。EUなどという壊れかけの脆弱な政治体を歴史(学)の対象とするということがどういうことなのか。そうすると、どのようなアプローチ上の工夫が必要なのか。それは、フツーの素材とどう類似し、また相違するのか。人文研における歴史や思想のプロの方々にぶつけて、そんなことを考えるきっかけにしたいと考えています。それはちょうど、かつて補完性原理の分析から、EUは思想の課題たりうるかという問題を検討した試みとパラレルのものとなるはずです。
出発点となるのは、この長き不在の間に公刊した3冊の編著、2008年の『ヨーロッパ統合史』『原典ヨーロッパ統合史』(名大出版)と2011年の『複数のヨーロッパ』(北大出版)です(参考文献として何か一冊というと『ヨーロッパ統合史』、どれか一論文というと『複数のヨーロッパ』所収の「ヨーロッパ統合史のフロンティア―EUヒストリオグラフィーの構築に向けて」3-41頁をベースにします)。