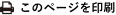戦争神経症は精神分析に何をもたらしたか
立木康介
2007年12月10日
精神分析の内部やその周辺では、第一次大戦中の「戦争神経症」の観察が、フロイトによる「死の欲動」概念の導入のきっかけとなったという通説が広まっている。私たちはまず、この通説を覆すことをめざし、「死の欲動」の導入はむしろフロイト理論に内在するいくつかのロジックの帰結であり、それなくしては戦争神経症が「死の欲動」に結びつくことはなかっただろうという見通しを示した。しかし、もしそうだとすれば、当時の精神分析は戦争神経症をどのように理解したのだろうか。戦争神経症について書かれたフロイトの弟子たち(フェレンツィ、アブラハム)の論考を繙くと、彼らがこの神経症を他のいわゆる「転移神経症」(ヒステリー、強迫神経症など)と同じ枠組のうちに捉えようとしていることが分かる。つまり彼らは、戦争神経症にとってもセクシュアリティが不可欠な条件であることを強調しているのである。この事実は、上述の通説と密接に結びついたもうひとつの通説をはっきりと否定する。その通説によれば、戦争神経症において、精神分析はセクシュアリティによって説明されるのとは別のタイプの「心的外傷」に出会った、というのである。しかし、じつはそうではない。精神分析はあくまで、明白なショック体験だけによって心的不調を説明することを拒み、その一歩奥へと、すなわち、セクシュアリティの傷というかたちで症状の普遍と主体の個別とが交わる地点へと、踏み込んでゆかねばならない。「心的外傷」をめぐる現代の一般的言説から、これはなんと隔たっていることか!
食糧戦争:「カブラの冬」の教訓
藤原辰史
2007年11月26日
第一次世界大戦期のドイツでは、イギリスの海上封鎖、食料価格の暴騰、労働力や肥料の不足などにより、約75万人が飢餓と飢餓を直接的な原因とする病気のために死亡した。とくに1916年から1917年にかけての冬は、銃後の民衆が飼料用のカブラを食べながら飢えを凌いだことから、「カブラの冬Kohlrubenwinter」と呼ばれている。本発表では、この「カブラの冬」の原因のみならず、ヴァイマル時代の農業経済学者やナチスの農本主義者たちに与えた「教訓」に着目し、その歴史的意義を検証した。
比米日三角関係史のなかの第一次世界大戦:日米戦争へと至る道
早瀬晋三
2007年11月18日
従来の東南アジア史では、政治的には戦場となったヨーロッパの植民地宗主国の影響力の低下から独立運動が活発になり、経済的にはヨーロッパ製品の品薄を補うかたちで日本製品が進出してきた、と言われてきた。いっぽう、アメリカ合衆国は、植民地フィリピンを中心に着実に東南アジアでの影響力を強めていった。フ ィリピン革命以来のフィリピンの親米派と親日派の動向をふまえ、第一次世界大戦の日米関係への影響とその後を考える。
ヨーロッパにおける第一次世界大戦関連モニュメント、資料紹介
2007年10月29日
古典主義運動と不定形なもの:第一次世界大戦前後のフランス文学
2007年10月13日
認識と決断:第一次世界大戦前後のドイツにおける「文化科学」の変貌
2007年9月24日
言語不信の文学:フランス戦争小説における口語文体
久保昭博
2007年7月23日
第一次世界大戦の戦中から戦後にかけて夥しく書かれた「第一次世界大戦小説」をひとつのジャンルと捉え、その文体的指標を求めると、口語文体という十九世紀末以来少しずつ姿を現してきた新たな言語表象が大規模に使われていることに気づかされる。本報告では、まず、この文体の成立の背後にあって、作家たちにも影響を与えた、シャルル・バイイら言語学者による口語研究を確認する。次いでこの種の文体が戦争という体験のリアリズム的表象に貢献していたことの証左として、戦時期に出版された各種の「兵士の俗語」辞典を検討する。これらのテクストが示すのは、様々な出自を持つ人びとが人類史上かつてない経験を共にする過程で、新たな言語が生み出されたという事実である。最後にアンリ・バルビュスの『砲火』(1916年)と、ルイ=フェルディナン・セリーヌの『夜の果てへの旅』(1932年)における口語文体の意義を比較する。バルビュスが口語文体をあくまでリアリズムの一要素として用いていたのに対し、セリーヌは、この大戦によって露呈した「言語不信」、すなわち自らの経験を語れないという事態を表現するために口語文体を用い、それによって小説言語に一大転換を生じさせた。
1877年と1914年を分かつもの:第一次大戦は最終露土戦争か?
伊藤順二
2007年7月15日
帝政ロシアは国内にドイツ系などの「敵性国民」を多数擁していた。政府高官や将校にもドイツ系の人物は多かった。敵性国民は国内での諸活動を制限され、一部は前線地帯から強制移住させられている。この状況はアルメニア人を多数擁していたオスマン帝国の状況と通底する。強制移住などの人口学的政策は、両国において1860年代からみられる。1914年以降の移住政策は露土戦争からの連続面を視野に入れて語るべきである。
塹壕の虚妄 ─アイルランドから第一次大戦を見る
小関隆
2007年6月25日
アイルランドと第一次大戦をめぐっては、2つのはっきりとしたイメージが存在する。1つは、アルスター・プロテスタントが「血の犠牲」をもってイギリスへの忠誠を尽くした、というユニオニストのイメージ、もう1つは、大戦に反対したナショナリストのイースター蜂起(同じく1916年)という「血の犠牲」がアイルランド共和国の礎石を築いた、というナショナリストのイメージである。しかし実際には、ユニオニストは大戦を支持し、ナショナリストはそれを批判した、というほど事態は単純ではない。大戦に際してIrish Parliamentary Partyが打ち出した、イギリスの戦争に協力せよとのナショナリズムの歴史上前例のない方針に応え、志願兵としてイギリス軍に入隊した人々は、たとえばイースター蜂起に関与した者たちよりもはるかに多かった。アイルランド史における大戦の意味を理解するためには、「ヒストリカル・ノーマンズ・ランド」に取り残されてきた「戦場のナショナリスト」の経験を改めて検討することが欠かせない。本報告では、ウィリー・レドモンドという人物をクローズ・アップする。彼はいかなる思いとともに従軍を決意したのか、そして、彼の戦場経験はいかなるインパクトを及ぼしえたのか、本報告の中核的な問いはこれである。
ヨーロッパ統合の遠い端緒:第一次大戦、米国、J・モネ
2007年6月 9日
音楽史における第一次大戦の「前」と「後」
2007年5月28日
第一次世界大戦研究のスコープ―世界性と総体性の二重性をめぐって
2007年4月28日