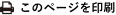第一次世界大戦と映画史 ―芸術としての映画から前衛映画へ
小川佐和子
2013年12月 9日
第一次世界大戦と映画の関係を考えるとき、第一に、プロパガンダとしての映像メディアに焦点が置かれるだろう。映画が、その誕生から帯びていた植民地主義、帝国主義、軍国主義のイデオロギーを踏まえ、ボーア戦争、米西戦争、日露戦争、バルカン戦争へといたる戦争映画の系譜を確認した上で、第一次世界大戦により、映像が「アクチュアリティー」から、イギリス・ドキュメンタリー運動の旗手であるジョン・グリアソン述べるところの「創造的処置を施したアクチュアリティー」へ、さらには「プロパガンダ」へと変容していく過程を見ていきたい。
(ここで扱う大戦映画の多くは次のサイトで閲覧可能である。http://www.europeanfilmgateway.eu)
さらに、映画史における第一次世界大戦の影響を考えるとき、通説として、ヨーロッパの映画先進国が衰退し、アメリカが映画市場を支配したことで、映画界の世界地図が塗り替えられたと言われている。そうした産業構造の変化と映画形式の規格化に加え、映画史を芸術史の立場から捉えると、大戦後、映画を自律した芸術とみなす意識が芽生え、主としてフランスおよびドイツで前衛映画の理論と実作が興隆していく。他方、一般の娯楽映画に見られる戦後の新たな傾向として、モダニズム―その光がハリウッド映画であり、闇に当たるのはヴァイマール期ドイツ映画―が生まれる。そして、アヴァンギャルドとモダニズムと左翼思想が結合したのが革命後のソヴィエト映画となろう。以上の流れを、大戦前の「芸術」としての映画から、大戦後の「伝統を廃棄する芸術」としての映画へ/空間芸術から時間芸術へ/物語の否定とメロドラマの増殖の双方向へ、といった観点から考えてみたい。いずれも第一次大戦がもたらした大きな波紋である。
第一次世界大戦下の日本における参戦経験と将来に対する期待
2013年11月25日
空間化する時間ー第一次世界大戦の文学表象と硬直化する経験
藤井俊之
2013年11月25日
第一次世界大戦への従軍経験をもつドイツ人作家たちのうち、現在最も読まれている作家のひとりは、間違いなく『西部戦線異状なし』を著したレマルクだといえる。当時の批評家によって、文学というよりはむしろ映画向きの叙述と揶揄されたこの作品は、しかし瞬く間に世界的ベストセラーを達成し、戦争のドイツ的表象を後々まで 決定する文学史上も極めて重要な小説となった。先の批評の言葉に皮肉を浴びせるように、事実ハリウッドでの映画化までなしとげたこの作品が出版されたのは、1929年のことである。戦後十年を経て現れたこの大ベストセラーを基準点として、その後の文学史には戦争文学をレマルク以前と以後に分類する考え方が一般的になっていく。そこで地滑り的に起こったのは、18年以後に兵士の日記や報告や回想といった体裁で書かれた戦地の状況伝達を主眼とする文学形式が、ワイマール共和国の安定化とともに影響力を喪失するという事態であった。今回の発表では、こうした戦争文学の形式の転換を考慮に入れつつ、とりわけレマルク以前に分類される作家から、エルンスト・ユンガーやゴットフリート・ベンといった戦争文学の文脈を離れて大きな影響力をもつ人物の諸作品を取り上げ、戦争と文学の関係を問うてみたい。
小シンポジウム:国なき民と「諸国民の戦争」
向井直己
2013年10月21日
パネラー:向井直己、鈴木健雄、長沢一恵、コメンテーター:小野寺史郎、中野耕太郎
War of the NationsからLeague of Nationsへ――第一次大戦の別称である「諸国民 の戦争」と、「国際連盟」が本来含意する「諸国民の連盟」の語は、「ネーション」と いう曖昧な概念が、大戦の経験を叙述し、理解し、総括するにあたって、当時からひと つの基礎的な単位として確立されていたことを示している。 むろん、「総力戦」として戦われた第一次大戦の研究にとって、統合された、或いは 統合へ向かう国民国家という単位は非常に基本的なものである。ウィルソンの「自決」 がいわゆる「民族自決」と解され、列強の支配下にあった諸国の独立に強いインスピレ ーションを与えたことも、当時のネーション概念が持ちえた強い求心力を物語っている 。しかし第一次大戦後の国際関係が、「諸国民」のネットワークとして成立すればする ほど、そこから零れおちてしまう一連の事柄がある。今回のシンポジウムは、そうした 「諸国民」の関係の隙間に落ち込んでゆく一群の人々、「国なき民」の戦後経験を捉え ることを主眼としている。 このテーマに即して若手研究者の間で討議を重ねる中で、以下の2点が主要な問題と して浮上してきた。すなわち、1)国家を持たない、或いは国籍を剥奪された人々の処遇 、2)国際社会に対し、未だ国家を持たない人びとを「代表する」ことのいかがわしさで ある。 1)に関して問題となるのは、とりわけ戦後社会における身分保障のない人びとの国際 的移動の難しさであろう。戦中、敵国の工作の監視・排除のために導入された旅券・査 証管理の厳格化は、戦後においてもそのまま継続され、ナンセン・パスポートの事例に 代表されるように「国民」からあぶれた人びとの地位を脅かすことになる。中東欧地域 における「ユダヤ人問題」への対症療法となっていたアメリカへの移民は、これを通じ て出口をふさがれた形となり、後のホロコーストを準備する一つの要因となった。 2)に関して問題となるのは、民族自決の基盤となる「被治者の合意」が誰によって、 どのような形で取り付けられるかという点である。制度的な基盤が脆弱な、或いは存在 さえしていない半-国家や「国なき民」にとって、国際的に承認される彼らの「正当な 」代表の権原はそもそも不確かなものであった。ヴェルサイユ体制においては朝鮮半島 の人民の利害が日本政府によって代理されたように、しばしば被治者の「正当な」代表 は彼らの独立と自決の可能性そのものを脅かす。 このシンポジウムは何かしらの結論を提示するというより、問題の存在を喚起するこ とを意図している。中野・小野寺からのコメントと、参加者各員の積極的な議論を通じ て視野をより多角化し、各国史の脈絡では捉えきれない問題について、より研究を深め る足掛かりとしたい。
総説:未完の戦争
小関隆
2013年2月20日
「精神の危機」の時代──古典主義・フランス・ヨーロッパ
森本淳生
2013年1月28日
第一次世界大戦終戦直後の1919年、ポール・ヴァレリーは『新フランス評論』(NRF)に「精神の危機」と題するエッセーを発表した。これは、1920-30年代にかけて盛んになる「ヨーロッパ精神」をめぐる議論の最初期に属する著名なテクストとなる。本発表では、NRFグループ、とりわけヴァレリーを中心にして、彼らを、状況の変化(精神の動員解除〜独仏和解〜ナチス台頭)や同時代の諸潮流(アクション・フランセーズ、ロマン・ロラン、共産党、キュビスム、ダダ、シュルレアリスム......)のなかに簡単に位置づけたうえで、「ヨーロッパ精神の危機」の内実を概観してみたい。それは端的に言えば、技術化の進行による精神の疎外の自覚と、政治・経済・精神の各領域で進行したヨーロッパの地位の相対的低下の意識であった。
「精神」espritという(少なくともわれわれにはきわめて曖昧に聞こえる)語は、ヴァレリーやジッドのドイツ・イメージ──近代機械文明の極致であると同時に、近代的主体が確立していない輪郭のぼやけた大衆──が逆照射するフランスを端的に示すものである。「精神」は、ヴァレリー的に言うなら、非合理的な力を確実な効果を伴う技術へと媒介する創造的な変換能力であった。こうした創造的な構築能力は、当時、右翼から前衛にいたるまで広く喧伝されるようになった「古典主義」において称揚されるものだった。しかし言うまでもなく、構築の背後にはおびただしい破壊があり、膨大な死者がいる。1921年に発表されたプラトン的対話篇『エウパリノス』のなかで、ヴァレリーが、冥界のソクラテスに建築を語らせていることの意味は、このように読み解けるのではないだろうか。
「フランス精神」によって価値づけられた「ヨーロッパ精神」は、ナショナリズムに対置されるのはもちろん、彼らが「没個性的」と呼ぶインターナショナリズムにも対置された。こうした「ヨーロッパ精神」は知識人のたんなる言説にとどまらず、具体的な文化活動としても具現化される。1924年5月の総選挙で左翼連合が勝利し、対独融和路線(ブリアン外交)への転換がなされたのと同時期に、フランスは、国際知的協力委員会(Commission Internationale de Coopération Intellectuelle : 1922年創設)に関連する独立機関として国際知的協力機関(Institut International de Coopération Intellectuelle : 1926年創設、ユネスコの前身にあたる)をパリに創設し、「知的協力」におけるフランスの主導性を確保しようとした。政治・経済における欧州協調への動きを文化面で反映するかたちで始まったこの活動の枠組みのなかで、1930年代、ヴァレリーらを中心として知識人による「談話会」や「往復書簡」が企画された。しかし、ナチスの台頭、国連脱退を前にして、文化レベルにおける交流を維持すべくあえて政治に触れまいとした彼らの知的協力活動は、人間の普遍的な価値を説いた点では評価しうるものの、対立の現実の克服する効果を持ち得なかった。エリート主義を色濃く反映する彼らの対話は、『エウパリノス』と同様、冥界での精神(esprit : 亡霊)の対話を思わせる。
ヴァレリーの言う「精神」の概念は、現在でも通用する普遍性を備えてはいるが、「精神の危機」が具体的に展開された文脈は、フランスのナショナルな価値と無縁ではなかった。国連知的協力活動も、フランス色を弱めより各国に開かれたかたちへと改革が試みられるものの、新たな大戦によって挫折を余儀なくされる。ヨーロッパの没落の意識とともに始まった「精神の危機」の議論は、ヨーロッパの普遍性を再建できぬままに終わりを迎える。
保養地と総力戦 ─第一次世界大戦期ロシア帝国のナショナリズム
池田嘉郎
2013年1月12日
はじめに第一次世界大戦期のロシア帝国について全般的な研究史を概観します。
ついで、大戦中のロシア帝国における保養地振興とナショナリズムという私の研究テーマについて、お話させていただきます。